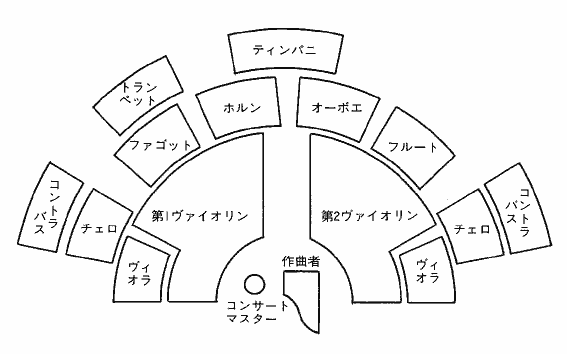
★本サイトは引っ越しました。5秒後にジャンプします。
ジャンプしない場合は、 ここ をクリックしてください。★
演奏会に出かけて、広いステージを埋めつくすオーケストラの姿を眺めたとき、その楽員達の並び方にまで思いを巡らされたことがおありになるだろうか。今日では、世界中のオーケストラは皆同じ様な楽器の配置を取っており、私達はそれをごく当たりまえのこととして受け止めている。しかし、現在標準とされている楽器配置が用いられるようになったのは、ここ半世紀ほどのことなのである。
オーケストラという語は、もともと古代ギリシャの円形劇場の中央部分、コロス(合唱隊)等の登場人物達が歌い踊る場所「オルケストラ」に由来する。一七世紀の初めにギリシャ劇を模してオペラというジャンルが作られると、まずその伴奏をする演奏者達のいる場所が「オーケストラ」と呼ばれ、次いで演奏者達の合奏自体もそう呼ばれるようになった。だが、その頃の「オーケストラ」にはまだ標準的な編成というものはなく、従って楽器配置も定まってはいなかった。
そもそも合奏の個々の楽器を作曲家が指定するということ自体、当時はまだ新しいことだった。ルネサンス時代までは、合奏曲は基本的に声楽(合唱)曲の編曲であり、演奏するパートの音域さえ合えば、自由に楽器を選択することが出来たのである。一般に楽器指定の最初の例とされているのは、ルネサンスからバロックへの過渡期にヴェネツィアで活躍したジョヴァンニ・ガブリエリの《ピアノとフォルテのソナタ》(一五九七)であるが、この曲は楽器配置の点から見ても興味深い。ここではコルネット一、トロンボーン三からなる第一群と、ヴァイオリン一、トロンボーン三からなる第二群が、いわば掛け合いをする。当時ヴェネツィアやその周辺で盛んであった二重合唱の様式を応用しているのであるが、ガブリエリがオルガン奏者を務めていたサン・マルコ大聖堂には、そうした音楽に相応しく左右に一つづつオルガンと聖歌隊の場所があった。従ってこのソナタも、各グループが左右に分かれて演奏し、聴衆はステレオ的効果を楽しむことが出来たのである。
もっと大きな、「オーケストラ」の概念に近い楽器指定の初期の例としては、モンテヴェルディのオペラ《オルフェオ》(一六〇七)が挙げられる。一〇本のヴィオールをはじめハープやオルガンなど種々の楽器が用いられ、初演時には三三人を必要とした。もちろんこれも標準的な編成とはいえず、配置も定かではないが、しかしこの曲では牧歌的な場面に用いられる楽器や地獄の場面で用いられる楽器など、担当する領域によって幾つかの楽器のグループがあり、恐らく奏したグループ毎にまとまって配置されたと考えられる。
ところで、オペラを生んだ一七世紀は、文化史の上ではバロック時代であり、政治的には絶対主義の時代であった。王侯貴族は豊かな宮廷生活を謳歌し、それを彩るために各地の宮廷で常設の楽団が生まれてくる。この常設化が、編成の標準化につながっていくことになる。当時最も影響力の強かったフランスの宮廷では、一六二六年、ルイ一三世によって「王の二四のヴァイオリン」と名付けられた楽団が組織される。文字どおり二四人の弦楽合奏で、宮廷内での礼拝や種々の催し物、オペラやバレーなどの音楽を担当した。二四人というのは、今日のオーケストラの規模から見れば小さいが、名称の中でことさら強調していることからも、当時はそれでもフランス宮廷の権威を象徴するに相応しい大規模な楽団と見なされていたことがうかがえる(実際、ルイ一四世のもとで活躍した作曲家リュリは、「二四のヴァイオリン」では大きすぎて合奏の質が落ちるからと、より小編成の楽団を別に組織している)。大規模なオペラやバレーなどでは管楽器の参加は不可欠であったが、管楽器には野外演奏を中心にする軍楽隊が別に組織されており、必要に応じてそこから人員が補強された。
バロック時代には、こうした宮廷楽団以外にも、とりわけドイツでは「コレギウム・ムジクム」という学生や市民による民衆的な演奏団体が活発な活動を行い(バッハもライプツィヒでその指導を行った)、イタリアではヴィヴァルディの指導する女子孤児院のオーケストラが優れた演奏で評判になっていた。宮廷楽団に於ける「弦楽器主体、管は必要に応じて追加」という編成の基本は、これらの演奏団体にも定着していった。
一方、その「配置」に関しては、当時の絵画資料などで見る限りかなり柔軟というか雑多であり、むしろ適宜その場の状況に応じて並んでいたらしい。恐らく最もよく行われていたのは、当時の音楽の土台としての働きを担っていた通奏低音楽器、チェンバロを中心にし、他の楽器はそのまわりで演奏する、という形であったろう。また、その頃はまだ一人(ないし二人)で譜面台を一本づつ用いるという習慣は一般的ではなく、大きな一つのテーブルの上に皆が譜面を置き、大勢で取り囲んで演奏している絵も結構ある。演奏の場、催しの状況などによっては、二階のバルコニーのようなところから広間を見下ろす形で演奏されることもよくあった。
一八世紀の後半、音楽史でいえば前古典派や古典派と呼ばれる時代になると、各地の音楽的交流も盛んになり、ようやく標準的編成も定まってくる。当時のオーケストラでは、とりわけマンハイム宮廷の楽団やパリのコンセール・スピリテュエルなどが有名であり、この他ロンドンやウィーンなどでも盛んにオーケストラ音楽が作られた。この頃には既にオーボエとホルン、ファゴットなどは殆どいつも用いられるようになり、祝祭的な雰囲気の音楽にはトランペットとティンパニが大抵一対のものとして用いられた。フルートは必ずという訳ではなかったがしばしば登場し、またマンハイム楽派は最新の楽器クラリネットをいち早く取り入れた。モーツァルトやハイドンは、こうした編成のオーケストラのために曲を書いたのであった。
こうして次第に「管弦楽」と呼ぶに相応しい編成が定まりつつある一方で、配置に関してはまだ固定的ではなく、柔軟かつ流動的な所が多かった。とはいえ、やはり基本となるのは、バロック時代と変わらず通奏低音楽器を中心に置いて、他の楽器をその廻りに配置するというものであった。通奏低音はこの頃には、楽譜の上のパートとしては次第に消滅しつつあったが、演奏習慣としては合奏のまとめ役として依然残っていたのである。この場合通奏低音を弾くのは多くの場合は作曲家自身であり、そうでなければコンサートマスター(ヴァイオリンの首席奏者)がヴァイオリンを弾きながら指揮役を務めた。
この頃の並び方の例として、ハイドンがロンドン旅行(一七九一〜三)で行った演奏会の配置を見てみよう(図1)。
図1: 1791-93年ロンドンにおけるハイドンの演奏会(ニール・ザスロウの復元による)
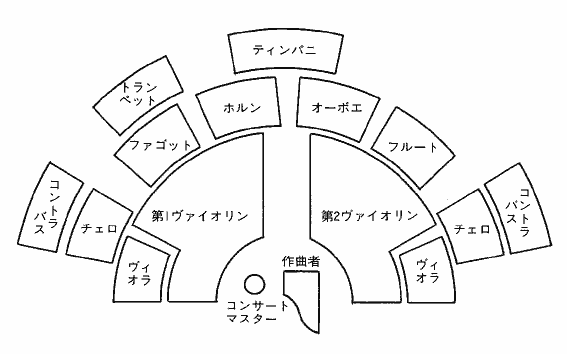
これは米国の音楽学者ザスロウが当時の資料をもとに復元したものである。永年務めたエステルハージ侯爵家の楽団が解散になり、自由な音楽家となったハイドンは、ロンドンの興業主兼ヴァイオリン奏者ザロモンに招かれて二度渡英し、大成功を収める。これはその最初の方のものである。作曲者の通奏低音及びコンサートマスター(ザロモン)を中心に、前面を弦楽器が取り囲み、後ろに管楽器及びティンパニが来る、という構図が見られる。弦楽が前、管打は後ろという配置は、今日の主要な配置にまでほぼそのま踏襲され続けているが、一つには「弦楽主体、管はあくまで付加的なもの」という歴史的経過の反映であると同時に、弦楽器と比べて管楽器の音の方がよく通る(音量も大きく、音色も鮮やか)ため、後ろに置いた方がバランスがよい、という理由からでもある。注目すべきは弦楽器で、第一ヴァイオリンと第二ヴァイオリンが左右に分かれているのはよいとしても、ヴィオラ、チェロ、コントラバスまでが左右に分けられていることである。左右から聞こえてくる音を同質化し、二〇〇年前にヴェネツィアでガブリエリが試みたようなステレオ感を生みだそうという意図であろうと思われる。なお、この時のオーケストラは総勢四〇人である。また、ハイドン二度目のロンドン旅行の際には、この編成にクラリネットが加わることになる。
一九世紀、ロマン派の頃になると、管楽器の発達が著しく、オーケストラで用いられる楽器の種類も増える。基本は古典派の頃と大差ないが、フルートとクラリネット、更にベートーヴェンの第五交響曲(《運命》)以降はトロンボーンが標準化する。ピッコロ、イングリッシュ・ホルン等標準的な楽器の同族楽器や、低音金管楽器(テューバ類)、更に種々の打楽器も用いられるようになるが、これらは必要な場合のみである。
それより大事な変化は、通奏低音が実践の上でも消滅したことである。鍵盤に向かいながら合奏をリードする存在がなくなると、その代わりを務めるのはまずはコンサートマスターだが、それでは荷が重いとなると、次に楽器を持たずにまとめ役に専念する人が現れる。指揮者の登場である。この指揮者が更に楽団の運営にまで力を及ぼすようになると、音楽監督と呼ばれる。一八三五年から四七年までライプツィヒのゲヴァントハウス演奏会の音楽監督を務めたメンデルスゾーンは、恐らくそうした存在の最初の一人に数えられるだろう。ここでは、彼の用いていたとされる配置を見てみよう(図2)。
図2: 1835-47年メンデルスゾーン時代のゲヴァントハウス演奏会
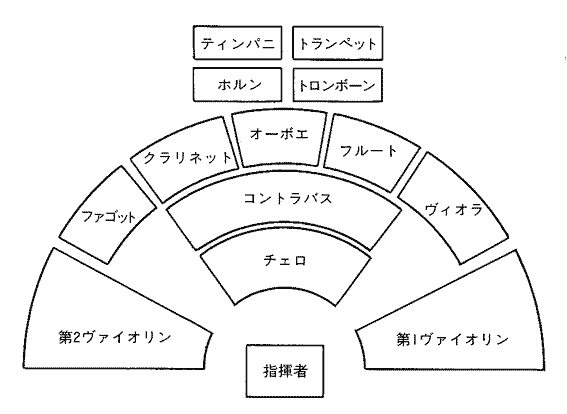
第一ヴァイオリンと第二ヴァイオリンが左右に、それも前面一杯に広がっている(第一の方が右にあることは注目される)。これは恐らく、弦楽合奏の響き全体よりも、ヴァイオリンの旋律性を表に出すことになるだろう。更に注目すべきは、チェロとコントラバスが中央にいることである、これは多分、かつて中央にいた通奏低音の代わりに、合奏の土台としての低音パートを据えたに違いない。だがこれは、ちょっと想像すれば解るように、あまり実用的ではないはずである。コントラバスのように大きな楽器、しかも立って演奏する楽器が中央に控えていたのでは、後ろの木管や金管は指揮が見えないではないか(しかもゲヴァントハウス・ホールには雛壇はなかったはずである)!本当にメンデルスゾーンがこの配置を一二年間用い続けたかどうかは定かではないが、少なくともこれは通奏低音消滅期の過渡的な試みであった。
しかしメンデルスゾーン方式の内、ヴァイオリンを前面に展開するというやり方は、つややかな旋律美を重視する一九世紀のロマン主義的音楽趣味の中で多くの支持を得た。そして図2から目障りなコントラバスを脇にどけ、全体を整えた形の図3の様な配置が登場してきた。
図3: 19世紀後半から20世紀初頭までのオーケストラ配置例
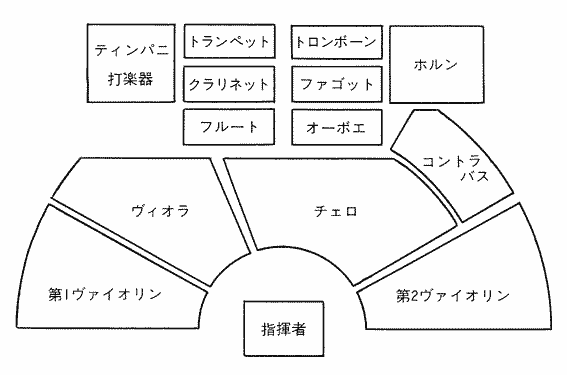
もちろんこの場合、コントラバスを左の方に持ってくることも可能だし(その時はチェロとヴィオラも逆になるだろう)、木管や金管の相互の位置関係は、変形可能である。いずれにせよ、第一ヴァイオリンと第二ヴァイオリンが一番前で左右向い合うという図3のような形は、一九世紀後半から今世紀に入るまで好んで用いられ続けた。
だが二〇世紀になって、もっと合理的な、あるいは音響(学)的な立場から、オーケストラの配置を見直そうとする人物が現れた。アメリカの指揮者レオポルド・ストコフスキーである。映画「オーケストラの少女」で有名な、そして独特の華麗な音楽作りで知られるストコフスキーは一九三〇年代から、いかにも彼らしい意図で、各楽器の持っている能力を無駄なく発揮し、効果的なめりはりに富んだ響きが生まれるような配置を工夫し続けた。彼は管楽器を弦より前に出したり、弦と管を完全に左右に分けたりなど、幾つものユニークな配置を提案しているが、その中で一貫して守り続けているのは、第一ヴァイオリンと第二ヴァイオリンを左右に分けず左側に固める、というやり方である。これには次のような利点がある。ヴァイオリンは奏者の左の肩にのせて弾き、従って響板(楽器の胴の板)は奏者の斜め右上方向を向く。音は響板の方向へ放射されるから、ヴァイオリンがステージの右側にいると音は客席ではなく舞台奥の方へ放射されることになる。だから第二ヴァイオリンの音を効果的に客席に届けるためには、第一ヴァイオリン同様ステージの左側に配置する方がよいのである。そしてそれによって、客席から見て左側は高音楽器、右側は低音楽器のまとまりが出来、音色のめりはりがより付きやすくなるのである。このやりかたを取り入れた配置の例が、図4に示すものである。
図4: 現代のオーケストラ配置例
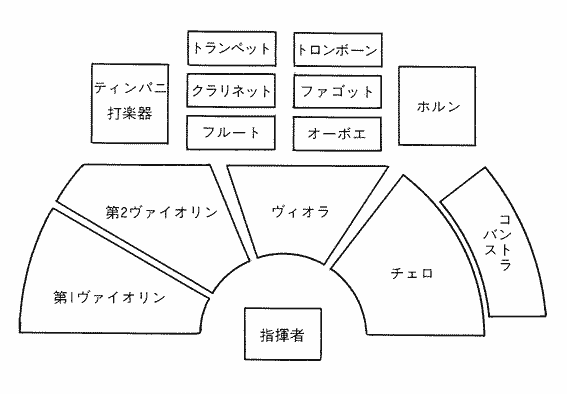
この配置は、今日殆どのオーケストラで採用されている。この図のヴィオラとチェロの位置を逆にしたものもしばしば用いられ、また管楽器の位置はやはり細かく色々と変化し得るだろうが、基本的なコンセプトに違いはない。
図3の配置は、前面にヴァイオリンのヴェールをかけることによって全体の響きを均一なまろやかなものとし、旋律美を重んずる。また、モーツァルトやハイドンが意図した左右のヴァイオリンの掛け合いの効果なども伝えることが出来る。一方、図4の配置は、個々の音色をあらわにし、原色的な色彩で、ダイナミックな表現を可能にする。ラヴェルやストラヴィンスキーのような華麗な作品は、こちらの配置でこそ存分に効果を発揮できることだろう。前者が一九世紀的なら、後者はいかにも二〇世紀的な配置といえようか。時代はオーケストラの並び方にまで影響を与えているのである。さて、二一世紀にはどのような配置が取られることだろうか。